子どもが思春期になると、家庭でどこまで学習をサポートすべきか悩みませんか?
特にゲームやSNSばかりで、なかなか勉強しないお子さんへの関わり方は難しいですよね。
思春期の子どもは、少しずつ親の手を離れ、自分の世界を持ち始めます。
それは嬉しい反面、「勉強しない」「反発ばかり」など、親として戸惑う場面も増える時期です。
私自身も、真面目な長女とマイペースな息子という性格の違う2人を育てる中で、関わり方に悩む時があります。

一方で、私の親は教育熱心で、思春期の頃はかなり過干渉でした。しかし、父が怖くて干渉が嫌とは言えず、従うことしかできませんでした。
猛勉強の結果、レベルの高い進学校に進みましたが、その反動で「厳しい環境から逃れたい」と感じるようになり、本当にやりたいことがわからなくなってしまいました。
だからこそ、今の私は自分の子どもたちに頭ごなしに「勉強しなさい」とは言わないと決めています。

親の言葉に従うのではなく、自分で考え、試行錯誤しながら成長していくことを大切にしています。
この記事では、思春期の子どもの学習における親の関わり方や、我が家で実際に効果を感じたオンライン教材の活用法を紹介します。
「勉強しなさい」と言わなくても、自分から動き出す子に育つ—そんなヒントをお届けします。
※この記事にはアフィリエイトリンクを含みます。リンクから商品やサービスを利用されると、運営者に収益が発生することがありますが、紹介内容は実体験と信頼できる情報に基づいています。
思春期の子どもの勉強、親はどこまで関わるべき?
子どもの勉強、放任すれば不安になるけれど、干渉しすぎると逆効果。
このバランスを取るのが、一番難しいところですよね。
子どもが勉強等のやる気をなくす一因は、“親が代わりに動きすぎる”こと。一方で、「本人に任せる」だけでは、子どもは迷子になることもあります。

過干渉は絶対にNG!
親の関わりが強すぎると、子どもの自立を妨げてしまうことがあります。
これは、私がお手本としているアドラー心理学やTRICKの法則でも語られています。
親が過干渉になると、子どもは人生の目標を見失い、自己肯定感も下がってしまいます。
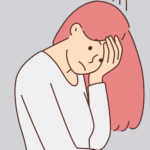
私自身、過干渉な父に育てられたので、とても辛い思いをしました。
私が思春期の頃、父は勉強の仕方や時間、休日の過ごし方まで全てを決め、それに逆らうことは許されませんでした。
その結果、学年トップクラスの成績を得て、父に従うことは得意になりましたが、自分で考え、行動する力が育ちませんでした。
社会人になってからも、自分に自信が持てず、会議などで意見を求められても答える事が苦手でした。
親の過干渉が「自分で決める力」を奪ってしまう事を、身をもって学びました。
「放任」しすぎてもNG

過去の経験から、子どもには“勉強しなさい”と言わないと決めていました。
自分が受けた過干渉の反動で、“自由に育てたい”という思いが強かったのです。
長女は真面目な性格で、私が何も言わなくても自分から勉強に取り組みます。弟は反対に宿題以外の家庭学習は一切しないタイプです。
その息子が、学期末の通知表で理科にC(最低ランク)がつき、落ち込んでいました。

そのとき私は、「宿題だけじゃなくて、テスト前に復習するといいんじゃない?」と伝えてみました。
すると息子は、
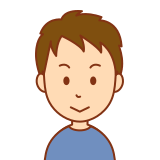
そうなのか!宿題だけじゃ良い点数は取れないんだね。
と、素直に反応しました。
どうやら、「テスト前に勉強しないと良い成績に繋がらない」という当たり前のことを理解していなかったようです。
子どもの知識や理解は、大人が思う以上にまだ浅いことがあります。
必要なときにそっと知識を補ってあげることが、本来の親の役割なのではないかと思います。
大切なのは“バランス”と“信頼”
自分の子ども時代に経験した「過干渉」と、自分の子どもたちに試してみた「放任主義」。
この両方を経て私が学んだのは、親がすべてを決めるのでも、完全に放っておくのでもなく、
というバランスが大切だということです。


しかし、このバランスが難しいですよね…
次の章からは、子どもの行動パターン別に体験談から分かったことをお話します。
勉強しない思春期の子への対処法
勉強に身が入らず、ゲームやSNSばかりという思春期のお子さんは少なくないと思います。親としてどうサポートするべきか、悩みますよね。

今の「勉強しない状態」を否定しない
「テスト前なのに全然勉強しない…」
そんな子どもの姿を見ると、つい「ゲームばかりして!」と注意したくなります。
でも、そこで否定してしまうと、
「勉強しない自分はダメなんだ」と感じ、自己肯定感の低下に繋がる事があります。
私自身も中学生のころ、父から「勉強しない奴は怠け者だ」と言われ続け、「勉強以外のことに興味を持つ自分はダメなのか」と感じていました。その結果、大人になってからも「何かを学んでいないと価値がない」と思い込む癖がついてしまい、自分の“好き”を見失う時期がありました。
だからこそ、我が家では「勉強しない」状態を否定せず、まず受け止めるようにしています。
ありのままの自分を認めてもらうと、子どもは安心します。そして、親のアドバイスに耳を傾けるようになるものです。
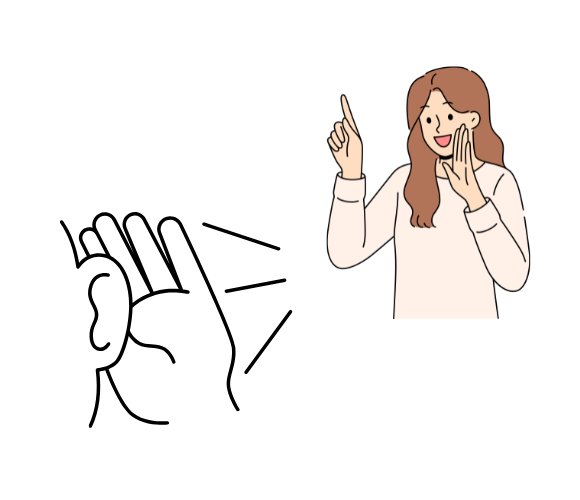
勉強していない理由を一緒に考える
子どもの状態を受け止めた後は、「どうして勉強しないのかな?」と、そっと理由を聞いてみてもいいかもしれません。
中学生の場合、“勉強しない理由”は怠けではなく迷いであることが多いと思います。
たとえば――
この3つが主なパターンです。
私の娘も、勉強方法に迷ったり内容が理解できなかったりすると、「休憩~」と言いながらSNSの動画を長時間見てしまうことがあります。
そんな時のやり取りがこちらです。

今日は動画ばっか見ちゃったよ~

そっか、そんな時もあるよね。

もぉ~。明日は携帯見ない!!

携帯見ちゃう原因があるのかな?分からない問題があるとか?

うーん、数学の問題解くのに時間かかって、疲れちゃって…
娘の場合は、勉強中につまずくことで集中力が切れてしまうのが原因でした。
このように、勉強しない理由を深掘りしてみると、「したくない」以外の要因が隠れていることも多いものです。
理由を受け止めて、提案する
理由がわかったら、否定せずに受け止めたうえで提案します。
たとえば、先ほどの娘の場合
- 問題の解き方をもう一度復習する
- 勉強する時は携帯をそばに置かない
といった提案をしてみました。
この時のポイントは、「~しなさい」という命令口調ではなく、「~してみるのはどう?」という提案口調で伝えることです。
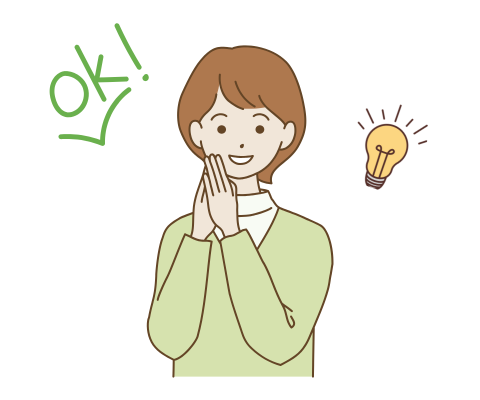
もし提案の内容が思い浮かばない時は、一緒にネットで調べてみたり、CHAT GPTなどのAIに相談してみるのも良いと思います。
子どもがどうしたいかを確認する
提案をした後は、子どもにこれから「どうしたい?」と確認してみます。
中2娘の場合は、
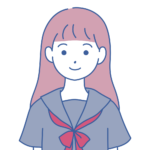
そうだね、復習してみる!携帯は今度からお母さんに預けるよ
とすんなり提案を受け止め、実行に移すようになりました。
子どもがこちらの提案を受け入れなかった場合は、「では〇〇はどうしたいかな?」と子供の意見を引き出してみてください。
そして、子どもの意見に賛成できなくても、危険が伴う内容でなければ、一度子どもの思うようにさせてみるのも良いと思います。
たとえば、小6息子の通知表に悪い成績がついた時、オンライン家庭教師を勧めましたが、息子は乗り気ではありませんでした。
そこで、

じゃあ、どんな方法が良いかな?学習アプリかな、それとも塾に行ってみる?
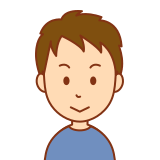
家で問題集とかやる
正直、「それでは続かないのでは…」と思いました。息子の性格上、塾か個別指導の方が向いていそうだったのです。
しかし、再度提案しても息子の気持ちは変わらない様子。

問題集や参考書で成績上がるように頑張ってみるんだね?
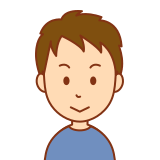
うん、がんばる!!
とのこと。
それから、息子は1日にどれだけ何をやるのかを決め、実行するようになりました。
日によって忘れることもありますが、そんな時は軽く声をかけるだけ。基本は息子に任せています。
正直、この方法では成績アップは難しいかもしれません。
それでも、息子が自分で決めたことを続けていく経験こそが大切だと思っています。まずは1学期間、その様子を見守ることにしました。
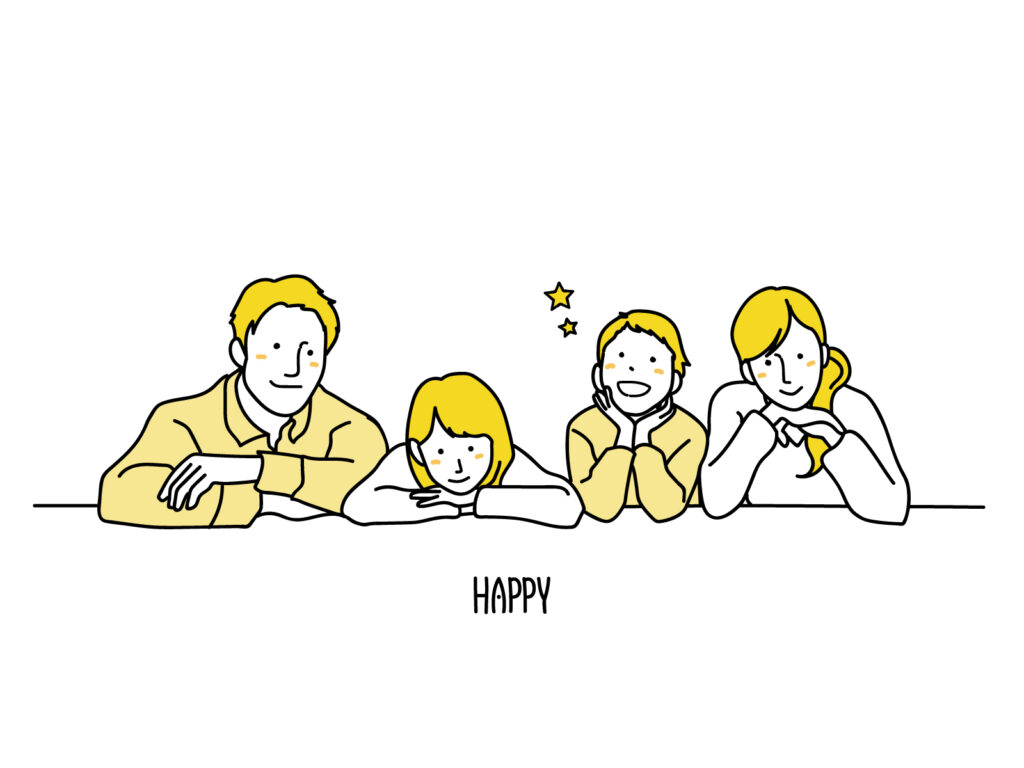
まとめ 信頼して待つことが一番のサポート
勉強しない子へのサポートは、「勉強させる」ことではなく、信頼して待つこと。
親が焦らず、理由を聞き、提案し、そして選択を任せる。
良い成績だけを目標にするなら、この方法は遠回りに見えるかもしれません。けれど、この流れを続けることで、子どもは少しずつ「自分の意志で動く力」を育てていくのではないでしょうか。
そして、失敗しても「次にどう対処するか」を繰り返すうちに、本当の意味で賢く・強い大人に成長できるのだと思います。
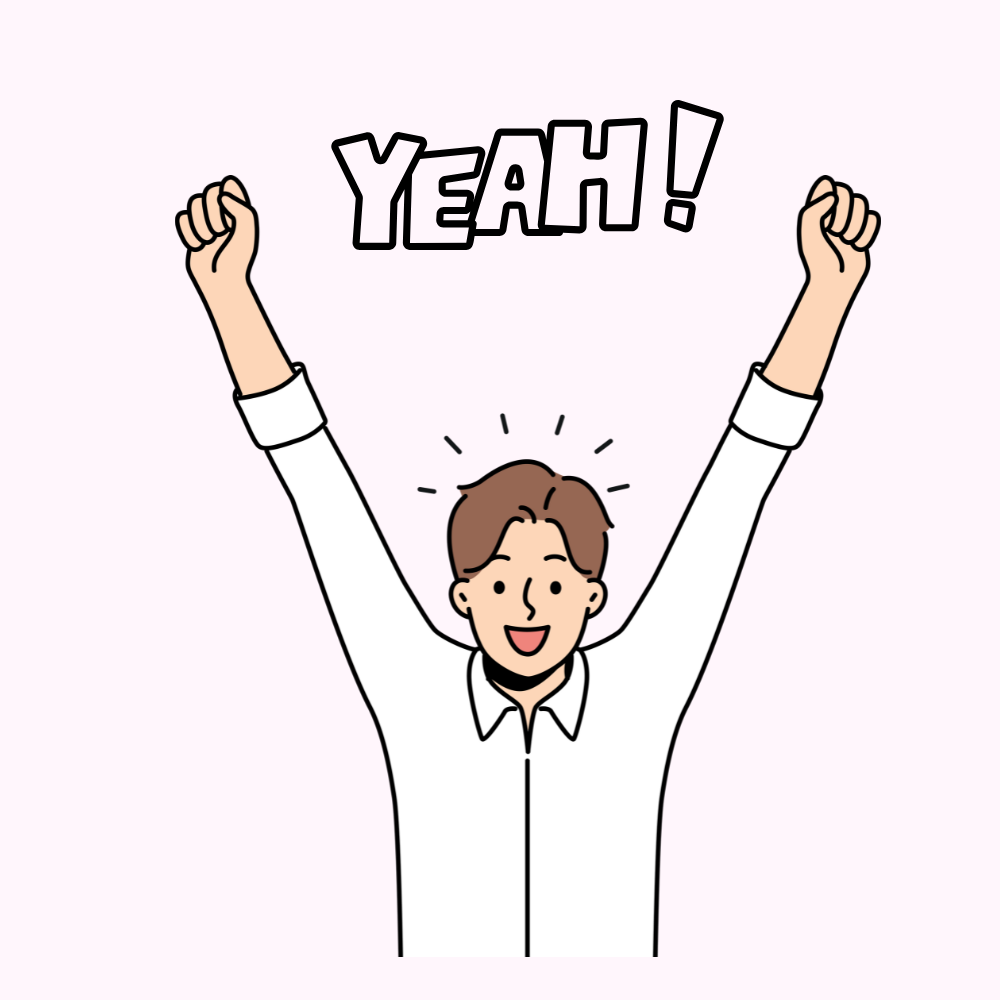
勉強を頑張っている思春期の子へのサポートの仕方
一方で、勉強を頑張っている子どもに対して、親ができることはあるのでしょうか?
我が家の場合、中学2年生の長女は真面目な性格で、宿題はもちろん、定期テストにも前もって計画を立てて勉強するタイプです。
一見、何も心配がなさそうに見えますが、真面目な分だけ精神的に追い詰められやすく、テスト前になると気持ちが不安定になってしまうことがあります。

そんな時、私がどのように対処しているかをお話ししますね。
テスト前にイライラしている子への接し方
真面目な子ほど、テスト前はプレッシャーでイライラしがちです。
私の娘も、言葉がきつくなったり、弟に当たってしまうことがあります。
そんな様子を見ると、つい注意したくなります。
すると、「そんなことわかってるよ!」と強く言い返され、娘は余計にイライラが増した様子。そして私もモヤモヤ……。悪循環になってしまいました。
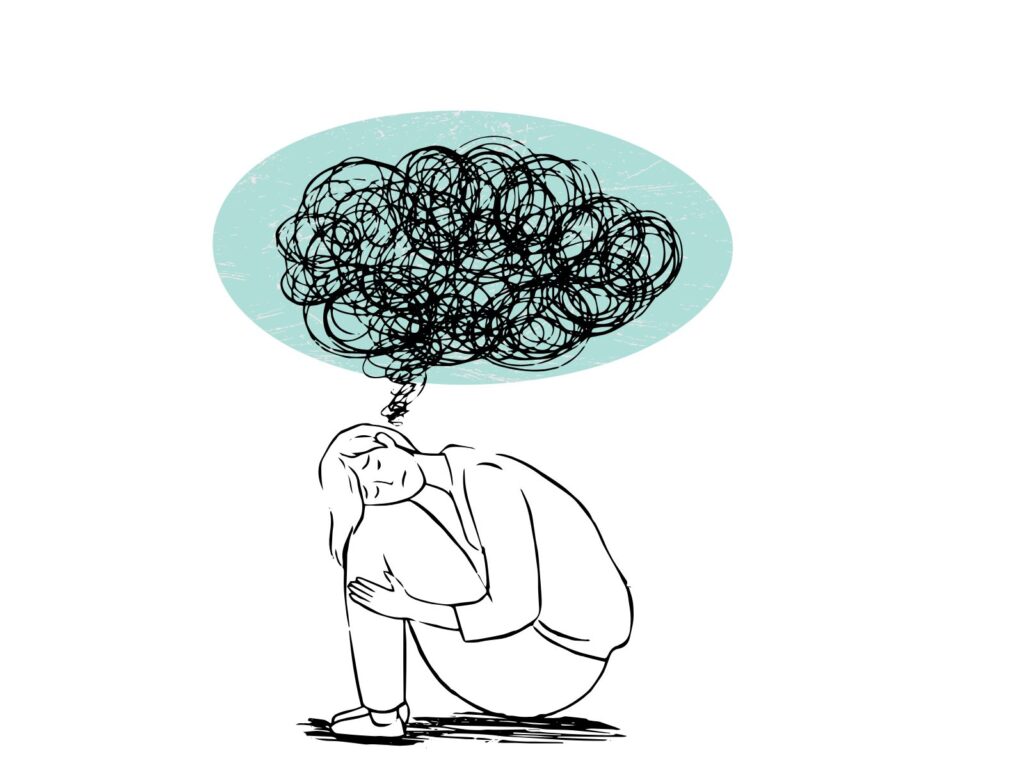
その経験から学んだのは、子どものイライラには反応しすぎないことが一番の得策だということ。
最近では、娘のイライラにも、ぐっと堪えて反応せず、別の時に「お疲れさま、頑張ってるね」と、努力を受け止める言葉をかけるようにしています。
すると少しずつ、娘の表情もやわらいでいくように感じます。
ただ、自分が我慢することで母親のストレスが溜まりがちになってしまうで、リフレッシュや自分へのご褒美で自分を労ってくださいね。
テスト結果が悪かった子への接し方
どんなに頑張っても、テスト結果が思うようにいかない事はよくあるものです。
我が家の子どもたちも、テスト結果を見て「頑張ったのに〜」と落ち込んでいることがあります。
そんな時、まずは「がんばったね」と伝えるようにしています。
そして

「分からないことがあったら相談してね」
と声をかけます。
また、普段から点数の良し悪しに関係なく、結果よりも過程を労うようにしています。
そうすることで、「親に褒められるから勉強する」という意識から、「自分のために勉強する」へと変わっていくのではと思います。
これは、私が大切にしているアドラー心理学の考え方です。
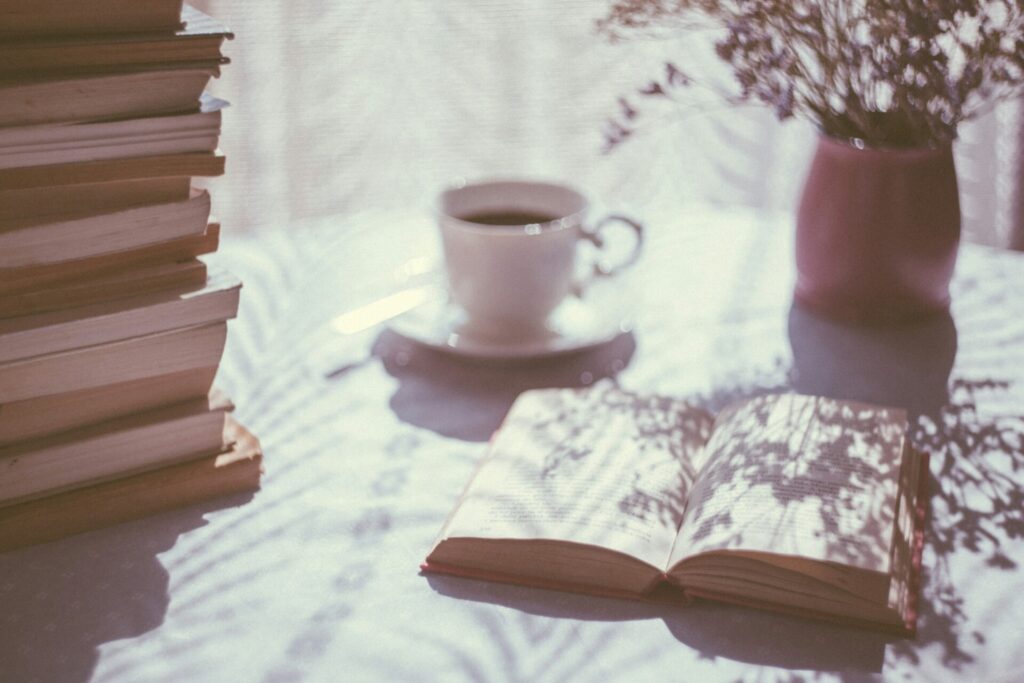
テスト前に特別にしてあげること
勉強を頑張っている子どもに、日々の努力をさりげなく支えることも親ができる事の1つだと思います。
我が家では、娘の定期テスト前には子どもの好きな食べ物を少し多めに用意しています。
人は美味しいものを食べると、心が癒されたり、「もうひと頑張りしよう」と思えたりします。
たとえば、娘の好きなお菓子を買ってきたり、夕食には好物メニューを出すようにしています。
すると、勉強で疲れていた娘にも自然と笑顔が戻ります。

単純なことのようですが、こうした小さな応援が、思春期の子どもの支えになると感じています。
勉強を頑張っている子どもに必要なのは、メンタル的なサポート。イライラも落ち込みも、頑張っている証拠です。
私たち親ができるのは、静かに見守りながら、温かい言葉と小さなご褒美でエールを送ることだと思います。
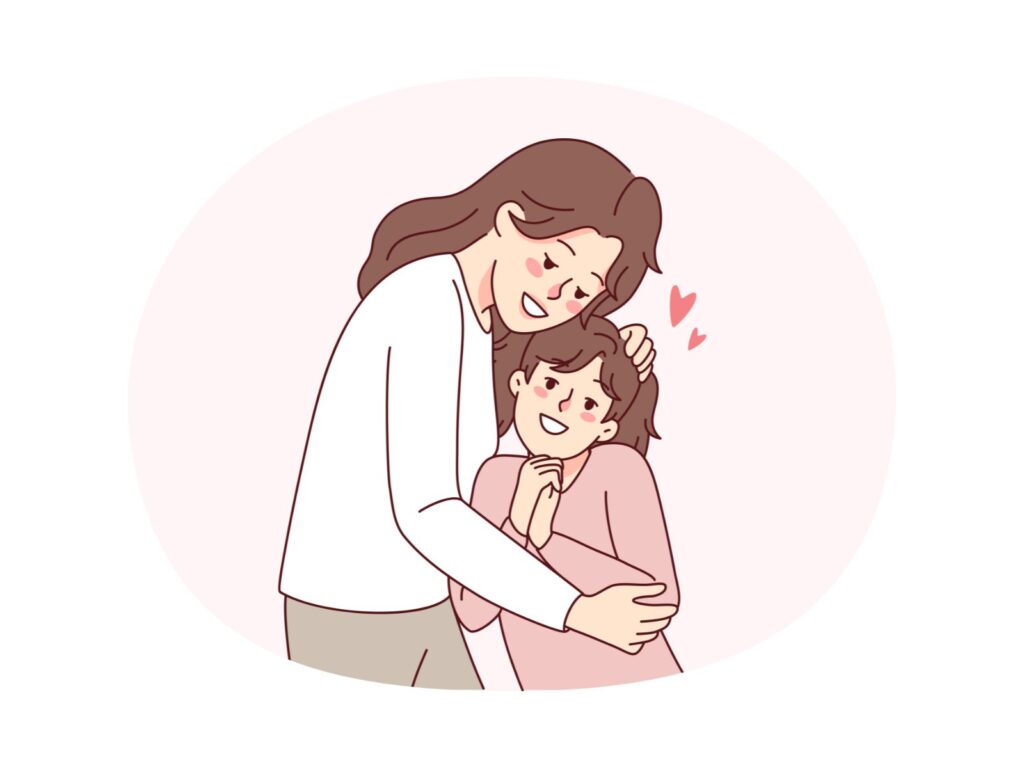
思春期の勉強をサポートする便利ツール
これまで、思春期の子どもの勉強を精神面からサポートする方法をお話ししてきました。
ここからは、実践面で親ができるサポートについて紹介します。
まず前提としてお伝えしたいのは、親が子どもに直接勉強を教えるのは避けた方が良いということです。
これは、私自身の子ども時代の経験と、現在の子育てを通して感じたことでもあります。
親が子に勉強を教える過程で、感情や甘えが入り込み、親子関係の悪化につながることがあります。
親は「良くなってほしい」という思いから熱くなりすぎて、「こんなにしてあげているのに」と責めてしまうこともあります。一方、子どもは親に甘えてしまい、つい反抗的な態度を取ることもあるでしょう。
それは、親子だからこそ起こる自然なことだと思います。
だからこそ、実際に勉強を教える部分は第三者のプロに任せるのが最も良い選択です。
とはいえ、塾や家庭教師は金銭的・時間的な負担が大きいもの。
そこで、現代の素晴らしい発明――「IT」を味方につけてみてはいかがでしょうか。

スタディサプリ中学生講座(5教科を自宅で効率学習)
我が家の中2の長女は、普段の学習に「スタディサプリ」というオンライン教材を使用しています。
「スタディサプリ中学生講座」は、リクルートが提供するオンライン学習サービスで、自宅で定期テストや高校受験の対策ができる映像授業型の教材です。
プロ講師による5教科(英・数・国・理・社)の授業が見放題で、副教科にも対応(追加料金なし)。月額2,178円(税込)でスマホやタブレットからいつでも学べるので、部活で忙しい中学生や、塾代を抑えたい家庭にも人気です。
娘は中1のときから受講していますが、
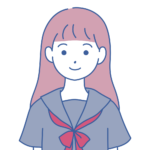
先生の授業が面白くてわかりやすいし、自分のペースで学べる
と気に入っています。
親としても、塾の送り迎えが不要なことや、家計に優しい料金は本当にありがたいポイントです。
ネイティブキャンプ(英語を楽しく続けるオンライン英会話)
「ネイティブキャンプ」は、24時間いつでもレッスンが受けられるオンライン英会話サービスです。
月額6,480円(税込)でレッスン受け放題・予約不要。思い立った時にすぐレッスンできるため、気分やスケジュールに合わせて続けやすいのが魅力です。講師は世界140か国以上から在籍しており、初心者から英検・スピーキング対策まで幅広く対応。
「英語を話す楽しさ」を感じながら学べるので、思春期の子でもリラックスして続けやすいサービスです。
娘は小5のときから中2の現在まで続けており、今年7月には英検2級に一発合格しました。楽しく質の高いレッスンを自分のペースで受けられることが、この結果につながったのだと感じています。
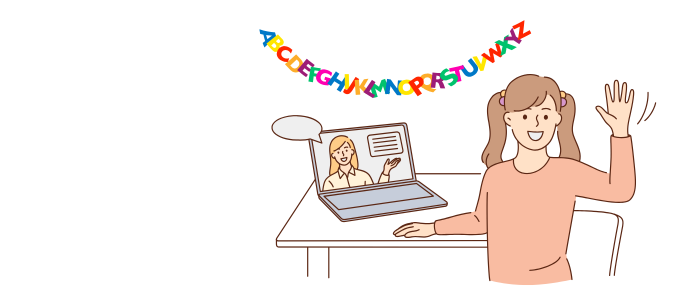
また、ネイティブキャンプの詳しい体験記事もありますので、興味のある方はこちらをご覧ください。

※サービス内容・料金などは2025年10月時点の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。
ChatGPT(質問・作文・調べ学習のサポートに)
「ChatGPT」は、質問に答えたり、文章をまとめたりできるAIチャットツールです。
わからない単語や文法の説明、理科や社会の調べ学習、作文の構成アドバイスなど、
子どもの“わからない”をその場で解決してくれます。
特に思春期の子どもは、親には聞きづらいこともAIには素直に聞けることが多く、
学習の自立を促すツールとしてもおすすめです。
我が家では、小6の息子が作文の校正に、娘が数学の質問や英検ライティングの練習に活用しています。
最初にChatGPTへの質問の仕方を教える必要はありましたが、子ども達はすぐに使いこなせるようになりました。
以前は「AIを使うと考える力が落ちるのでは」と心配していましたが、「学習モード」では、単に答えを教えるのではなく、CHAT GPTと対話を通して子どもが自分で考えるよう導いてくれます。
今では我が家の家庭学習の「もう一人の先生」として欠かせない存在です。
このように、我が家の子どもたちはオンライン教材+AIを上手に活用しています。
息子は作文が苦手でしたが、少しずつ文の構成を理解し、まとまった文章が書けるようになってきました。
娘は塾に通わず、英検や部活、趣味の時間も楽しみながら、安定して良い成績を保っています。勉強と自分のやりたい事とのバランスを保ちながら努力できる姿に、親としてとても成長を感じています。
そして何より、親子ともに時間に縛られず、子どもが楽しみながら学べるのが最大の利点です。学校の成績だけでなく、「自分で考え、行動する力」を育てる学び方だと実感しています。

まとめ “手を出さない勇気”が思春期の自立を育てる
思春期の勉強サポートで一番大切なのは、「信じて待つ」ことだと感じています。
親が手を出さずに見守ることで、子どもは自分で考え、失敗から学び、少しずつ自立していきます。
もちろん、心配になる瞬間は何度もあります。
でも、思春期の子どもたちは、親が思っている以上に自分なりに成長しようともがいているものです。
私たち親にできるのは、安心して挑戦できる環境と、静かに見守る姿勢を整えることではないでしょうか。
オンライン教材やAIツールを上手に活用すれば、子どもは自分のペースで学びを深められます。

親は「教える人」ではなく、「応援し、支える人」へ。そう思えるようになってから、我が家の家庭学習もずっと穏やかになりました。
思春期の学びは、結果だけを追う時期ではなく、「自分で考え、動き出す力」を少しずつ育てていく過程だと思います。
もちろん、今の社会では成績や受験という現実も避けられません。
それでも、自分で考え行動できる力を持っていれば、どんな環境でも前に進める。そんな力こそが、これからの時代を生き抜く“学力の土台”になると感じています。
※本記事の内容・料金等は2025年10月時点の情報です。
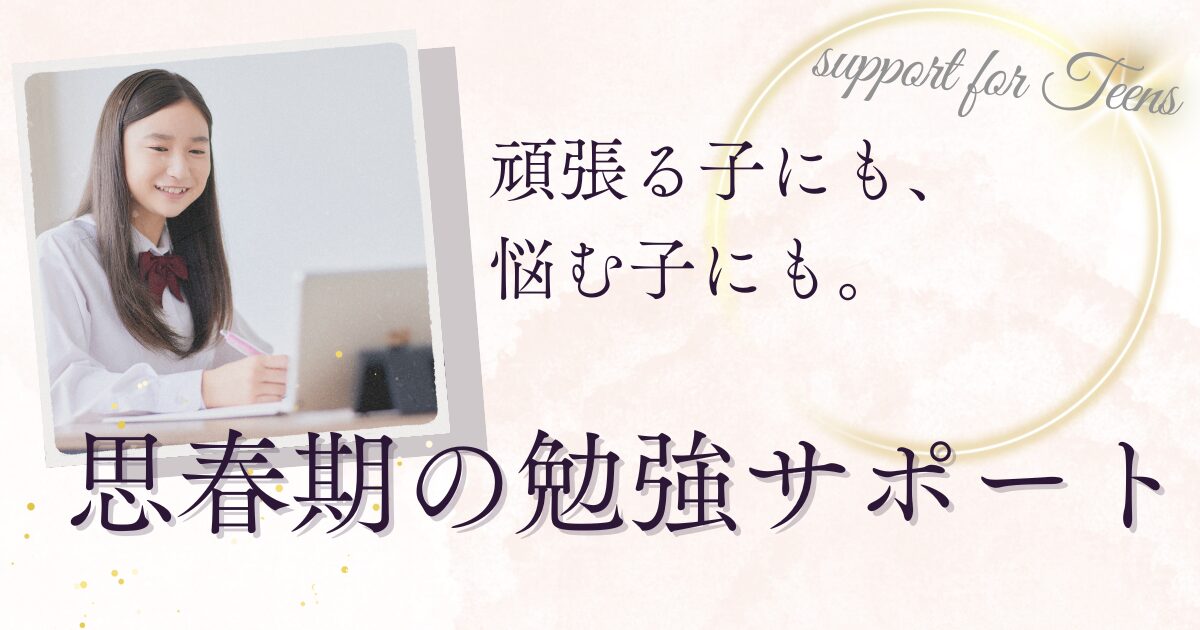
コメント