思春期のお子さんとの関係に悩んでいませんか?
思春期は、大人と子どもの間で心が揺れ動く時期。好きなものがはっきりしてきたり、学校や友達との関係で葛藤を抱えることも少なくありません。
そんな彼らは、部屋にこもってスマホやゲームに夢中になっていたかと思えば、急に甘えてきたりと、気持ちも行動も読めないものです。
そんなとき、次の3つのことを意識して関わることで、親子の距離がグッと近づくのを実感しています。
私自身、思春期には親との関係で苦しい思いをしました。
「好きな物事は否定される」「親の考えを押し付けられる」「甘えることができない」

そんな状況で育ち、自信も自主性も持てない日々を送っていました💦
だからこそ、自分の子どもには同じ思いをしてほしくないし、親子で良い関係を築きたい。
そんな思いから、本を読んだり、実際に試行錯誤したりしながら、関わり方を学んできました。特に、「アドラー心理学」や「TRICKの法則」から多くのヒントを得ています。
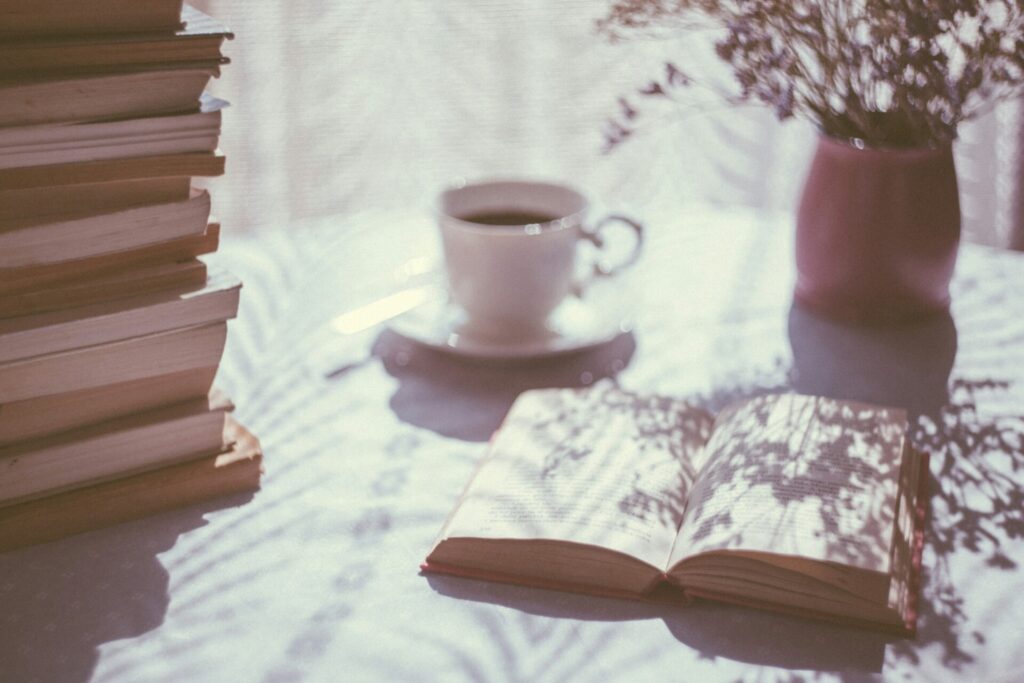
実際に上記の3つの事を実践すると、衝突は減り、子供たちは家でのびのびと過ごすようになりました。それぞれの「好き」に自信を持ち、私や夫との関係も良好です。

では、私が実際に試して効果を感じた「3つの関わり方」を、実体験を交えて詳しくお伝えします。
思春期の「好き」を受け止める
思春期の子どもが夢中になっている「好き」を、親がそのまま受け止めてあげることは、とても大切です。
というのも、思春期の子どもたちにとって、「好き」はただの趣味ではなく、自分らしさを育てる大切な軸だからです。
たとえば、推し活やアニメ、ファッション、YouTube等のSNS、ゲーム…。
大人から見ると「そんなことばかりして…」「もっとためになることをしてほしい」と思ってしまうかもしれません。
でも、それは子どもにとっての“世界”であり、“表現”なんだと思います

実は私も子どものころ、テレビや漫画、おしゃれをすることが大好きでした。
でも父親から「くだらない」と言われて、とても悲しかったのを覚えています。
好きなものを否定されると、まるで自分自身を否定されたような気持ちになるんです。
そしてそれが続くと、「親を不機嫌にさせる私はダメなんだ」と感じてしまい、 次第に「自分の居場所はここにはない」とまで思い詰めていました。

だからこそ、私は今、子供たちの「好き」が、自分にとってピンとこなくても、否定しないように心がけています。
たとえば、うちの息子はとにかくゲームやYou Tubeが大好き。
空いた時間はゲームするか、You Tubeを見るか・・という、いかにもイマドキの小学生です。
目のために休憩は促しますが、
時々「それ面白そうだね!」とゲームそのものに興味を示すような言葉をかけるようにしています。
すると息子は「そうだよ~!お母さんもやってみる?」と嬉しそうに言います。

本当は一緒に遊ぶのが一番いいのかもしれません。

ですが私はゲームが得意ではなく、その役割は夫に任せています。
このように、子どもの「好き」を否定せず、少しでも興味を持って寄り添ってみること。
それが「認めてもらえた」という気持ちにつながり、子どもの自己肯定感が育っていくのだと思います。
もちろん、人を傷つけることや危険な事は受け入れてはいけません。
でも、そうでない限り、「それ、いいね」と共感してあげる。 そんな関わりが、思春期の心にとって、いちばんの安心になるのではないでしょうか。
思春期に押し付けはNG!
子どもには、親の考えを一方的に押し付けるのではなく、子ども自身のタイミングや気持ちを尊重することが大切です。
特に思春期の子供たちは親の考えを一方的に押し付けられると、とても窮屈に感じます。
特に、進路や勉強といった重要なテーマであっても、子どもが「今は聞ける状態じゃない」と感じている時に繰り返し言われると、大きなストレスになります。タイミングが合わなければ、どんなに正しいことでも届きません。


また、勉強等を強要されることは、私自身が経験してきたことであり、とても辛い思いをしました。
思春期の時に進路について親から繰り返し「国公立の大学に入りなさい」と言われ、毎日長時間の勉強を強いられました。自分の考えや希望は受け入れてもらえませんでした。今でもその時のつらさははっきりと覚えています😔
だからこそ、自分の子どもには「勉強や習い事は強要しないし、進路は自分で考え、自分で決めてほしい」と心に誓っていました。

…でも最近、気がつくと私自身も、娘に進路の話をつい熱心にしすぎてしまっていたんです💦
中学2年になった娘の周りでは「受験」「塾」の話題が出てきて、私も焦ってしまったのだと思います。
良かれと思って話しかけたものの、娘の反応は薄く、「あ、今じゃなかったな」と気づいて反省しました。
子どもにも、「話を受け取れるタイミング」があるんですよね。
そんな娘が最近、図書館で『僕たちはまだ仕事のことを何も知らない』という本を借りて、熱心に読んでいました。
他にも、子ども向けの金融漫画を手に取っていたりして、彼女のタイミングで“将来”について考えているのが伝わってきました。
子どもは子どもなりに、自分のペースでちゃんと考えています。

だからこそ、親は焦らず、押し付けるのではなく、そっと見守る姿勢が大切なんだと、改めて感じました。
甘えと相談には受容と共感
思春期の子どもの気分は、コロコロ変わりやすいものです。(大人もそうですが…)
ツンツンしていたかと思えば、急に猫なで声で甘えてきたり、急におしゃべりになったりすることもあります。そんな時は、「チャンス!」と思って、思いっきり受け止めてあげる(受容する)
のがおすすめです。

これは私自身の思春期時代を振り返ってもそう感じます。
私は当時、学校のことや自分の考えを、あまり親に話さないタイプでした。父親や祖父母は厳しく、雑談や相談をするような雰囲気はありません。母は優しい人でしたが、いつも祖父母が周りにいて、話を聞かれたくありませんでした。
本当は思いっきり甘えてみたり、相談したいときもありました。
でも普段の家庭の雰囲気から、「甘えたり、自分の悩みを打ち明けても、受入れてもらえないだろう」と決めつけて、そうすることはありませんでした。それは、本当につらい時の「助け」がないと感じていて、寂しさもありました。
そんな経験から、子どもが甘えてきたり、普段言わないことを話してきた時は、無意識に「ヘルプ」を出しているんだと感じます。
普段からよく話してくれる子でも、「相談」って、なかなか日常的にはありませんよね?
だからこそ、「どう思う?」「○○なことがあって、どうしたらいいかな?」と話しかけてきた時は、しっかり耳を傾けてほしいんです。
ちなみに、私と娘は普段からアニメやイラストの話などはよくしています。
でも、学校での出来事についてはあまり話してくれません。
理由を聞いてみると、「お母さん、すぐママ友に話すでしょ〜?」と言われました(笑)
娘は、私がママ友といろいろ話す様子を見てきていて、そこに噂話も含まれていることを知っていたんです。
「なんて賢いんだ…!」と感心しつつ、反省もしました。そんなわけで、娘は学校のことはあまり話しません。
でも、先生の面白い話などは共有してくれますし、ごくたまに「実は○○ってことがあってさ〜」と話してくれることも。
そんな時は、全力で耳を傾けます。
「相談」された時は共感!
子どもから相談されたときは、「共感すること」が大事です。
意見やアドバイスを言いたくなってしまいますが、ぐっとその気持ちを堪えて、共感する事にしています。

あいづちや「そうなんだね」「それは大変だったね」といった共感にとどめるようにしています。
「どうしたらいい?」と聞かれた時は、「お母さんは○○したらいいと思うけど、あなたはどう思う?」と提案ベースで伝えます。
悩んでいる時って、必ずしも結論が欲しいわけじゃないですよね。
むしろ、「わかってもらえた」と感じることで、心が軽くなることの方が多い。
それは子どもも同じだと思うんです。
だからこそ、子どもの話にはアドバイスよりも、共感を。
「わかるよ」「それは辛かったね」と寄り添うことが、親としてできる大きな支えになるのではないでしょうか。

ただし、下記の3つの事が分かった時は、大人の判断でしかるべき対処が必要です。
- 健康に係わること
- 法に触れること
- 人を傷つけること

この3つの事が起きてしまったら、行政や専門家を頼りながら、じっくり向き合っていくのが良いと思います。
思春期の子どもがふと甘えてきたり、話しかけてくれたとき。
それは、きっと「今なら聞いてほしい」というサインなんだと思います。
いつも強がって見えるかもしれないけど、心の奥では親を必要としている瞬間があるんですよね。
そんな“かすかなヘルプ”を見逃さずに、ただそばにいて、話に耳を傾けてあげる。
それだけで、子どもにとっては「ちゃんとわかってくれる大人がいる」と思える大切な安心材料になるのだと思います。
まとめ
このように、思春期の子供との関り方には、大きく下記の3つポイントがあります。
- 思春期の「好き」を受け止める
- 思春期の子に押し付けはNG!
- 甘えと相談には受容と共感
この3つをおさえるだけで、子供たちと良い距離が保てるようになり、衝突することも減るのではないでしょうか。

実際、私もこの3つを心にとめており、実践することで子供と良い関係が築けています。
私のように、親から正反対の接し方をされて育ってきた人は、頭では理解しても衝動的に子供を否定してしまったり、自分の意見を一方的に伝えてしまったりしてしまうかと思います。
だからこそ、この注意点をしっかり落とし込んで、子供と接することが大事だと思います。
否定してしまったり、押し付けてしまっても、そのあと「ごめんね」と謝ったら大丈夫です!
わたしもついついやってしまった!という事はたくさんあります。でも、その都度、「ごめんね、つい心配で」と謝って、関係を修復してきました。

ちなみに、この「3つの大切なこと」は、アドラー心理学と、TRICKの法則から得たものです。
もしご興味があったら、下記の著書を読んみてくださいね。思春期子育てのヒントが沢山得られますよ。
- 『嫌われる勇気』
岸見一郎・古賀史健- 『TRICK』
エスター・ウォジスキー
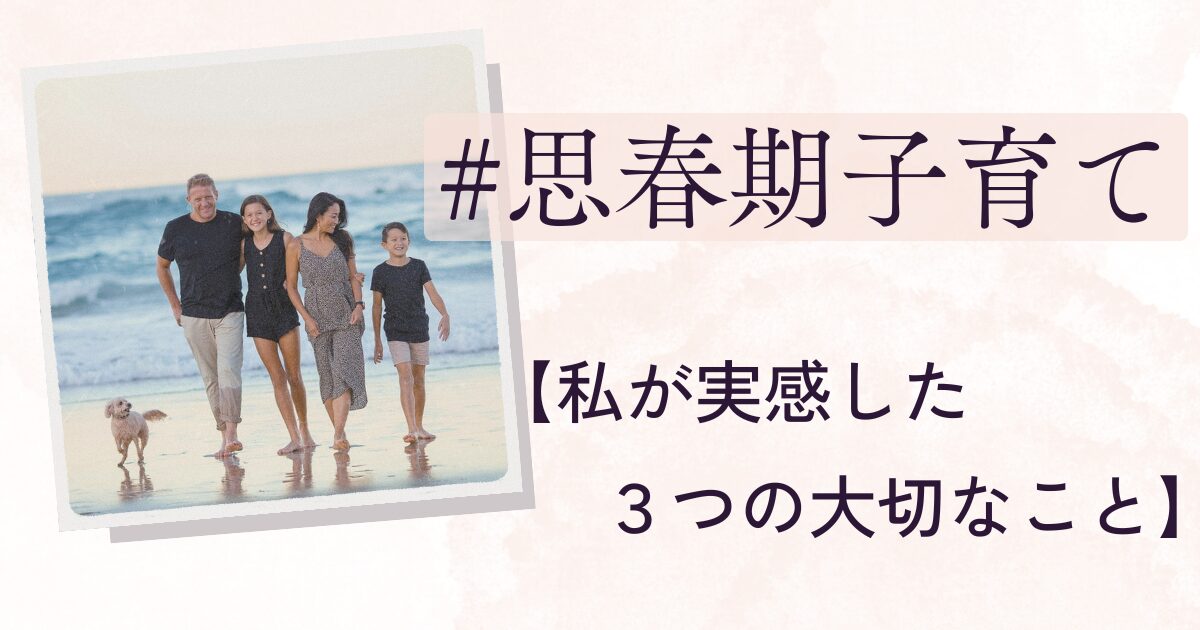
コメント